
私たちが感じる“疲れ”は、単なる「だるさ」や「眠気」では終わらないことがあります。これを放置して慢性疲労の状態になってしまうと、体のさまざまなシステムに支障をきたすようになります。
その中でも大きく影響を受けるのが「内分泌系(ホルモンバランス)」です。内分泌系が疲れることで、代謝をつかさどる肝臓、腎臓、膵臓、筋肉といった器官にも次第に負担がかかっていきます。
ホルモンの乱れが「代謝の異常」を引き起こす
内分泌系がうまく働かなくなると、体の中で必要なホルモンの分泌量が崩れてしまいます。すると、本来ホルモンによってコントロールされている「代謝の機能」も狂い始めるのです。
特に影響が出やすいのが、糖尿病や脂質異常症、痛風です。これらはすべて、「疲れがたまったからすぐに発症する」というものではありません。けれども、慢性的な疲労状態=ホルモンの乱れが続く状態を放置すると、病気につながるリスクが高まってしまうのです。
ご予約はオンラインからでも可能です。
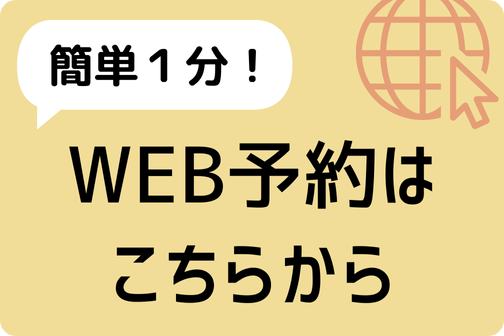
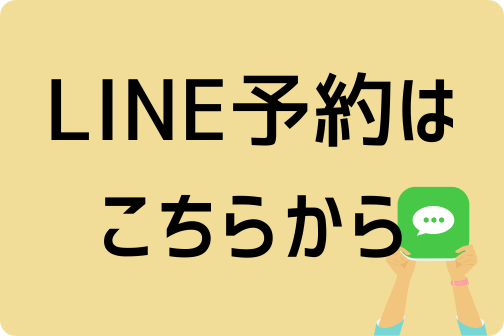
女性ホルモンと脂質の関係:コレステロールが高くなる理由
特に中年期の女性に多く見られるのが、健康診断などでの「コレステロールが高めですね」という指摘。これは、実はホルモンバランスの乱れによるものです。
女性は更年期に差し掛かると、エストロゲン(女性ホルモン)の分泌が徐々に減っていきます。エストロゲンは、善玉コレステロール(HDLコレステロール)を増やす働きを持っています。HDLは、悪玉コレステロール(LDL)や中性脂肪を体の外へ運び出す、大切な“掃除屋”のような存在です。
しかしエストロゲンが減ることで、HDLが減少。すると、LDLが増えてしまい、脂質異常症へとつながってしまうのです。
ホルモンバランスの乱れは「疲労のサイン」でもある
このように、慢性的な疲労はホルモンバランスを乱し、体の中で静かに病気の種を育てていくことになります。「ちょっと疲れやすくなった」「寝てもスッキリしない」といった日々の違和感は、単なる生活習慣の問題ではなく、内分泌系からのSOSのサインかもしれません。
参考元:東洋経済新報社「あなたを疲れから救う 休養学」






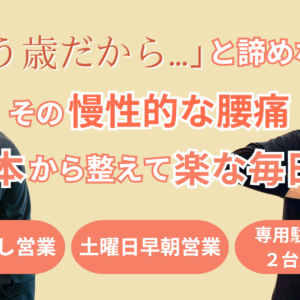
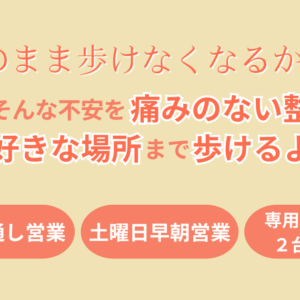
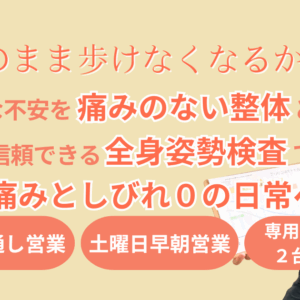






コメント