
休養にも「型」がある
ここまで「休養」の重要性や、攻めの休養の考え方をお伝えしてきました。では、実際にどんな休み方が疲労回復につながり、活力を高めてくれるのでしょうか。
そのヒントになるのが、「休養学」で提唱されている7つの休養モデルです。これは、休養のタイプを大きく3つに分類し、さらにそれぞれを具体的な方法で細分化したものです。
ご予約はオンラインからでも可能です。
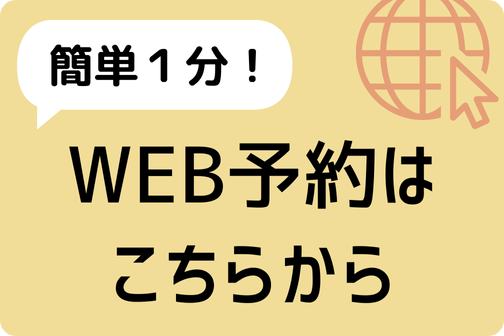
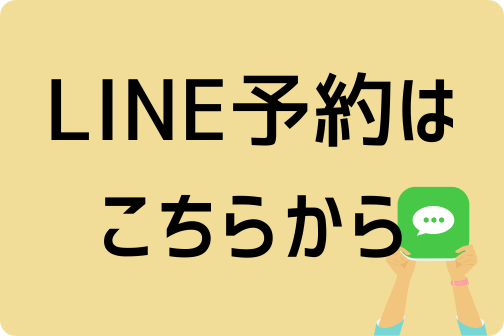
休養の3つの基本分類
まず、休養は次の3つに大別されます。
1.生理的休養(からだの休養)
2.心理的休養(こころの休養)
3.社会的休養(人との関係性からの休養)
この3つの軸に、それぞれ異なるアプローチがあり、合計で7つの休養モデルが存在します。今回はまず「生理的休養」の1つ目、「休息タイプ」について詳しく見ていきましょう。
生理的休養その1:休息タイプ
休息タイプの休養は、もっとも一般的にイメージされる「休む」方法です。
つまり、体を動かさず、エネルギーの消費を最小限に抑えることで、自然と体力が回復するのを待つという受動的な休み方です。これを別名、「消極的休養」と呼ぶこともあります。
代表的な休息行動
・睡眠(夜の睡眠+昼寝)
・休憩(座る・横になる・目を閉じる)
なかでも特に重要なのが「睡眠」です。体の疲労回復には欠かせないプロセスであり、特にサーカディアンリズム(概日リズム)に合わせて生活することで、睡眠の質は格段に向上します。
ご予約はオンラインからでも可能です。
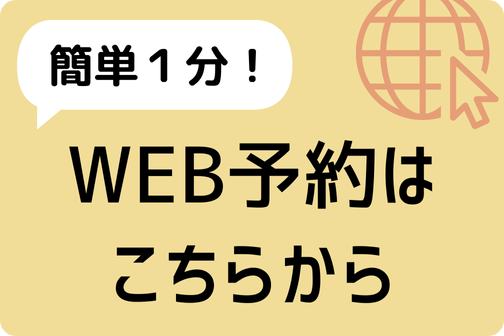
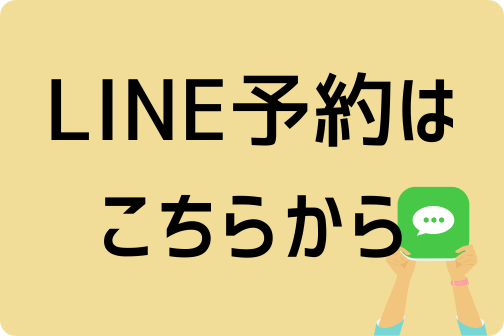
だらだら休養の落とし穴
ただし、気をつけたいのは「質の低い休息」です。
例えば、一日中ベッドでゴロゴロしたり、ソファに寝転んで動画や映画を何時間も見るなど。これらは一見「休んでいる」ようでも、実際にはエネルギーの回復にはあまり効果的とは言えません。なぜなら、これらは主体的ではない休養だからです。
疲労をしっかりと取るためには、「目的を持って休む」ことが大切です。
・「今日は体を回復させるために、2時間横になる」と自分で決める
・「睡眠不足を補うために昼寝を20分取ろう」と時間を区切る
こういった意識的・計画的な休息が、より深い回復につながるのです。
逆に、「何となく疲れてるからだらだら過ごす」という休み方は、結局疲労が残ったまま、休日が終わってしまう原因にもなります。
休息タイプの休養を、もっと戦略的に
「何もしない休み」も時には必要です。しかし、それが「戦略的」かどうかで、その効果はまったく変わってきます。
これからは、単にゴロゴロするだけでなく、「体力を回復させるための行動」として休むことを意識してみてください。次回は、生理的休養の2つ目、「運動タイプの休養」についてご紹介していきます。
参考元:東洋経済新報社「あなたを疲れから救う 休養学」






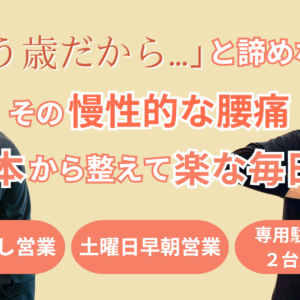
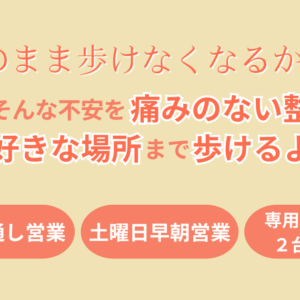
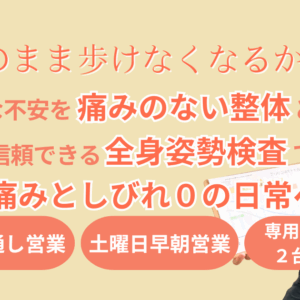






コメント