
「疲労の原因は、筋肉に乳酸が溜まること」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実際、「学校でそう習った」という声も少なくありません。ですが、現在ではこの説は誤りであることが明らかになっています。
では、なぜ「乳酸が疲労の原因」と言われてきたのでしょうか?
かつて、疲労の正体を探るために行われた実験では、被験者に100mを全力で走らせ、その直後に採血して血液中の成分を調べていました。すると、毎回のように乳酸が検出されたため、「乳酸がある=疲れている」と短絡的に結びつけてしまったのです。
乳酸が多く出るのは、主に無酸素運動をした時です。有酸素運動と違い、無酸素運動は非常に強度が高いため、運動後にはエネルギーが枯渇します。そこで体は、糖(グルコース)を分解してエネルギーを素早く補おうとするのですが、その際に出てくるのが乳酸なのです。
つまり、「疲れているときに乳酸がある」のであって、「乳酸が疲れの原因」ではないということです。
ご予約はオンラインからでも可能です。
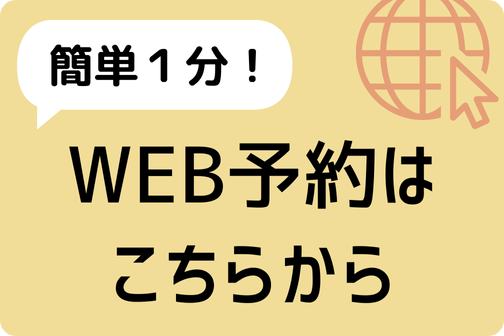
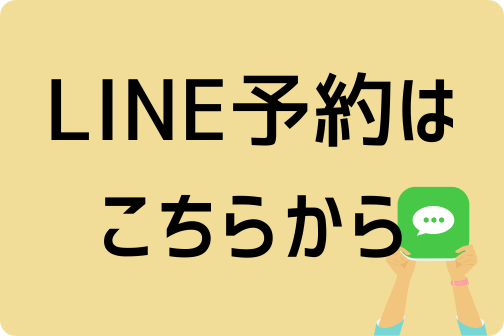
「疲労の正体」を知るために注目される測定法
かつては乳酸の量が「疲労のバロメーター」とされていましたが、現在ではそれに代わる特定の物質はまだ見つかっていません。ただし、疲労のたまり具合を判断するための方法として注目されているのが、「心拍変動解析」です。
私たちの心臓は一定のリズムで「トックン、トックン」と拍動していますが、よく見るとその間隔にはわずかなゆらぎがあります。このゆらぎを解析するのが心拍変動解析です。
この解析では、心拍の波のピーク間の距離を測定し、それを高周波(副交感神経の指標)、低周波(交感神経の指標)、超低周波の3つに分類して状態を把握します。ちなみに、超低周波についてはまだ明確な意味づけがなされていません。
交感神経と副交感神経、それぞれの数値の合計(トータルパワー)を指標とすることで、今の疲労レベルがある程度可視化できるようになりました。たとえば、村田製作所が販売している「疲労ストレス計」はこのトータルパワーを測定し、タクシードライバーや長距離トレッカーなどの疲労管理に役立てられています。最近では、スマホアプリで指先から簡単に自律神経の状態を測ることも可能です。
最も大切なのは「自分の感覚」
トータルパワーの数値は血圧と同じで、体調によって日々変動します。絶対的な基準にはなりませんが、疲労の目安としては有効です。
しかし、どんなに科学的な計測が進んでも、一番大切なのは「自分の体の声に耳を傾けること」です。数値に頼るのも良いですが、自分の感覚を信じて、無理をせず、自分に合ったリズムで過ごすことが何よりの疲労対策になるでしょう。
参考元:東洋経済新報社「あなたを疲れから救う 休養学」






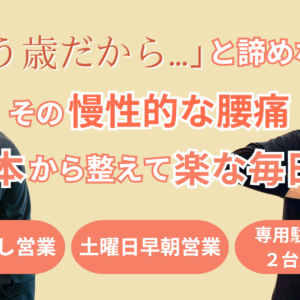
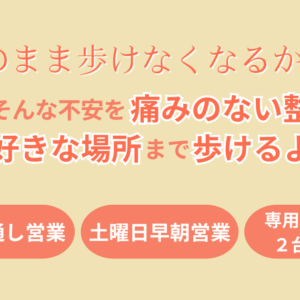
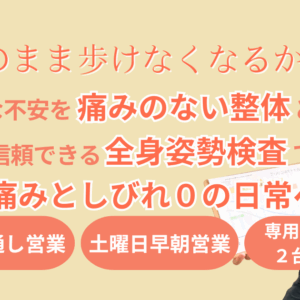






コメント