
「代謝の病気」と聞くと、まず思い浮かぶのが糖尿病ではないでしょうか。糖尿病には、大きく分けてⅠ型とⅡ型があります。
糖尿病の2つのタイプ
・Ⅰ型糖尿病
生まれつき、膵臓からインスリン(血糖値を下げるホルモン)が分泌されないタイプです。この場合、体外からインスリンを注射で補う必要があります。
・Ⅱ型糖尿病
こちらは、生活習慣が主な原因。食べすぎや肥満によってインスリンの分泌量が不足したり、インスリンの働きが悪くなる「インスリン抵抗性」が生まれることで起こります。これがいわゆる生活習慣病タイプの糖尿病です。
ご予約はオンラインからでも可能です。
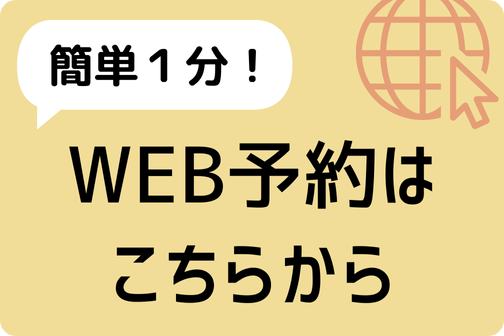
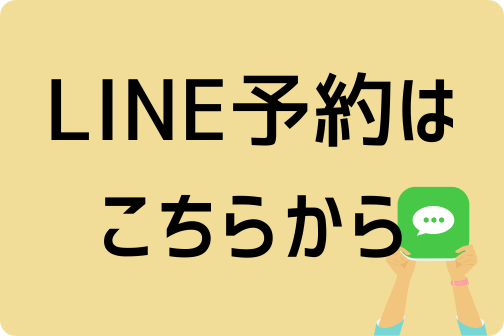
実は「ストレス」でも血糖値が上がることがある
ストレスを感じたとき、体は「緊急事態だ!」と判断します。すると、副腎からコルチゾールというホルモンが分泌され、エネルギー源として血糖値を上げようとします。
さらに問題なのが、インスリンの働きがストレスで鈍くなること。つまり、体は血糖値を下げにくくなり、ストレスが続くと血糖値が高い状態がキープされてしまうのです。
糖も“ストレス”になる?
「糖」は、エネルギー源として不可欠な栄養素ですが、摂りすぎると体にとっては逆にストレッサーになります。現代は「過食の時代」。知らないうちに糖質を摂りすぎている人が多いのです。
その結果、体の中で糖とタンパク質が結びつく=糖化が起きてしまいます。
体内で起こる「ホットケーキ現象」=糖化とAGEs
ホットケーキを焼いたときにできる、あのきつね色の焼き目。これは「メイラード反応」という現象で、糖とタンパク質が加熱されてできるものです。
実は同じようなことが、私たちの体内でも起きているのです。これを糖化(とうか)と呼び、糖化が進むと「AGEs(終末糖化産物)」という老化タンパク質が生成されます。
ご予約はオンラインからでも可能です。
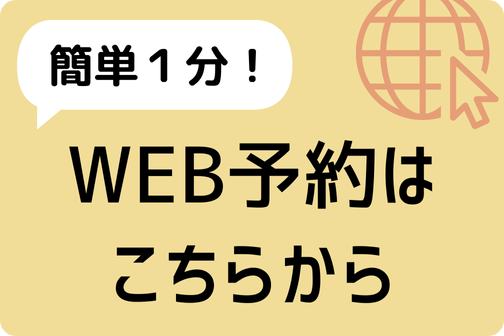
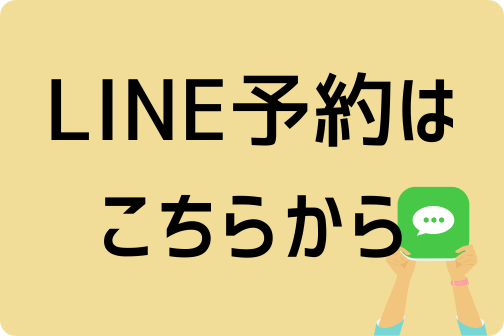
血糖値を急に上げない食べ方の工夫
糖の摂りすぎによるストレスや糖化を防ぐために、日常の食事でも工夫ができます。
特に意識したいのが「GI値」です。GI値とは、食品がどれだけ早く血糖値を上昇させるかを示した指標のこと。
・GI値が高い食品(白米、砂糖、菓子パンなど):血糖値が急激に上がる
・GI値が低い食品(野菜、きのこ、豆類など):血糖値が緩やかに上昇
最近では、「低GI食品」をうたったパンやお菓子も多く販売されています。野菜から食べ始めるベジファーストも、血糖値の急上昇を防ぐのに効果的です。
参考元:東洋経済新報社「あなたを疲れから救う 休養学」






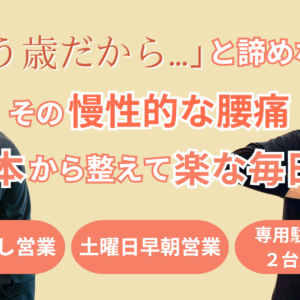
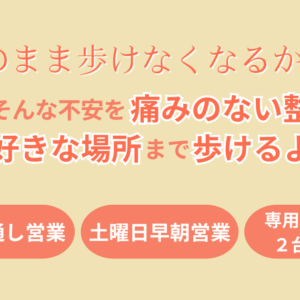
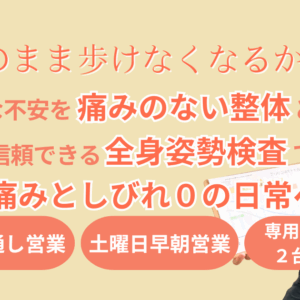






コメント