
疲労は軽視されがち
痛みや発熱があると、多くの人は「これは危険なサインだ」と直感的に理解し、適切な対応を取ろうとします。しかし、疲労に対しては同じように考えられることが少なく、無視されたり軽視されたりしがちです。
例えば、体のどこかが痛んだり、高熱が出たりすると、多くの人は「今日は休もう」と判断し、会社や学校を休むことをためらいません。上司や同僚も「無理せずにゆっくり休んで」と理解を示してくれるでしょう。しかし、「今日は疲れているので休みます」と言ったらどうでしょうか。多くの場合、周囲の反応は冷たく、「疲れくらいで休むの?」と一笑に付されてしまいます。
本来、疲労も体が発する重大な警告であり、休養が必要なサインです。それにもかかわらず、多くの人が疲労を無視し、無理をして頑張り続けてしまうのは、「疲労感が覆い隠されてしまう」ことが大きな要因です。
疲労感は「マスキング」される
人間には、使命感や責任感、仕事のやりがい、褒賞への期待などによって、疲労感を一時的に覆い隠す能力があります。これが「疲労のマスキング」です。
例えば、スポーツ選手が「この試合に勝てば、大きな報酬がもらえる」と言われると、どれだけ疲れていても限界を超えて頑張ることができることがあります。また、「ここで頑張らなければ、チームのみんなに迷惑をかける」と考えると、疲労を感じていても体を動かしてしまうでしょう。これは、脳が疲労感を一時的に感じにくくさせる働きを持っているからです。
この能力自体は、人間が困難な状況を乗り越えるための素晴らしい仕組みでもあります。一時的にどうしても頑張らなければならない場面では、とても有効に働くでしょう。しかし、この「マスキング」を繰り返し続けると、自分の疲労に気づかなくなり、気づいたときには回復に時間がかかるほど疲労が蓄積してしまっている、という事態に陥ります。
ご予約はオンラインからでも可能です。
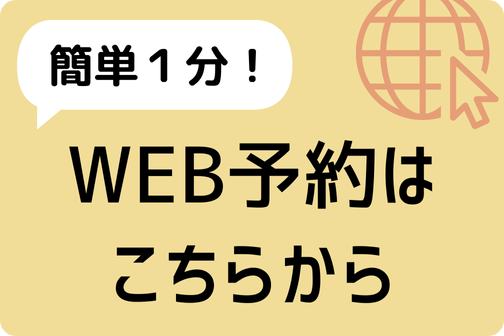
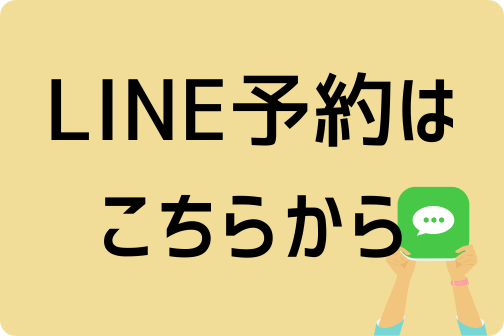
疲労を無視し続けるとどうなるか
疲労感を無視し、十分な休養を取らずに活動し続けると、少し休んだくらいでは疲れが取れなくなります。そして、慢性的な疲労が蓄積していくと、次第に体調不良を感じるようになります。
最初は「なんとなく体が重い」「寝ても疲れが取れない」といった軽い症状かもしれません。しかし、その状態が続くと、自律神経が乱れ、免疫力が低下し、ついには病気へとつながることもあります。過労が原因で重い病気を引き起こしてしまうケースも決して珍しくありません。
疲労感を正しく受け止める
私たちは、痛みや発熱には敏感ですが、疲労には鈍感になりがちです。これは、疲労感がマスキングされやすい仕組みを持っているからです。しかし、「疲れたから休みたい」と思うことは決して甘えではなく、体が発する正当なサインなのです。
「疲労感は危険信号である」という考え方が広まれば、社会全体で「疲れているなら休むべきだ」という意識が根付くかもしれません。私たち自身も、「自分は疲れていない」と思い込むのではなく、自分の体の声に耳を傾け、適切に休息を取ることが、健康を守る第一歩なのです。
参考元:東洋経済新報社「あなたを疲れから救う 休養学」






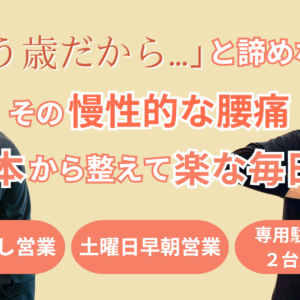
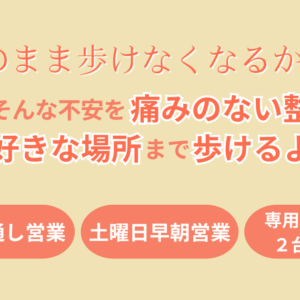
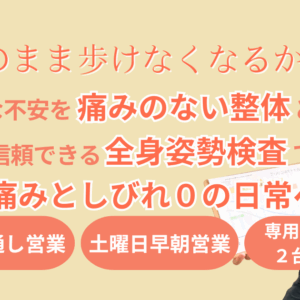






コメント