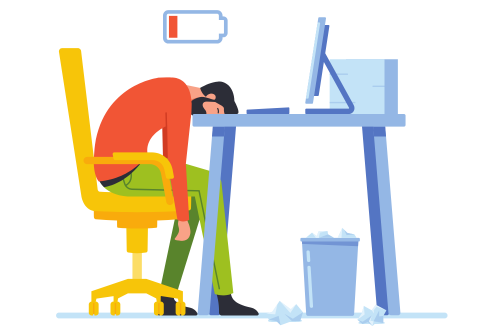
疲労には3つの段階がある
疲労には「急性疲労」「亜急性疲労」「慢性疲労」という3つの段階があります。急性疲労は、1日から数日しっかりと休めば回復するような軽度の疲労です。例えば、スポーツをした翌日に筋肉がだるく感じたり、仕事が忙しかった日の夜に強い眠気を感じたりすることがこれに当たります。適度な休養や睡眠をとることで、比較的短期間で解消されるのが特徴です。
しかし、疲労が長引き、数週間から数か月にわたって続くと、亜急性疲労の段階に入ります。この状態になると、単に寝るだけでは回復せず、「しっかり休んでいるはずなのに疲れが抜けない」と感じることが増えてきます。仕事や家事の負担が続くことで、休養をとる時間が確保できないことも影響し、慢性的な疲れを感じるようになります。この段階で適切な対処を行わないと、疲労はさらに深刻なものへと進行してしまいます。
半年以上も疲れが抜けない状態になると、それは慢性疲労と呼ばれます。この段階では、疲れの原因がはっきりしていることが多く、「仕事のしすぎ」や「運動のしすぎ」など、疲労の積み重ねによって体が悲鳴を上げているのです。慢性疲労はそのまま放置すると、さらに深刻な健康問題へとつながる可能性があります。
ご予約はオンラインからでも可能です。
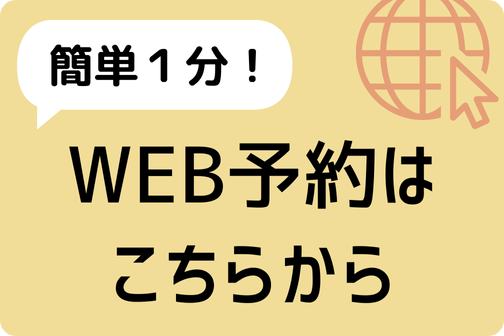
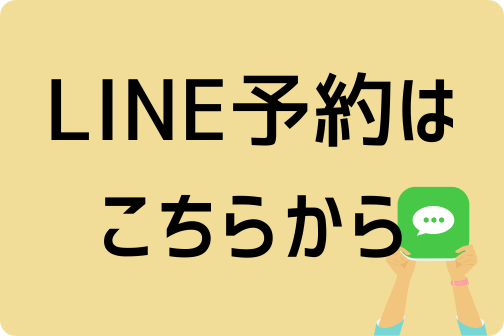
慢性疲労と慢性疲労症候群の違い
似た言葉として「慢性疲労症候群」という病気がありますが、これは慢性疲労とは異なります。慢性疲労は、原因が明確であり、十分な休息をとれば回復する可能性があります。しかし、慢性疲労症候群は原因が明確でないことが多く、脳や神経系に影響を与える病気です。強い倦怠感が半年以上続き、休んでも改善しないのが特徴で、頭痛や発熱などの症状を伴うこともあります。単なる疲れとは違い、生活に支障をきたすほどの強い症状が続くため、医療機関での適切な診断と治療が必要になります。慢性疲労症候群という名前は最近、「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)」という名称に変わりました。
疲労を放置すると健康リスクが高まる
疲労を軽視することは非常に危険です。疲れを放置すると、免疫力が低下し、風邪をひきやすくなったり、自律神経が乱れて不眠や動悸を引き起こしたりすることもあります。また、ホルモンバランスが崩れることで、生理不順や更年期症状の悪化につながることもあります。さらに、精神的な負担が増すことで、ストレスや不安、抑うつ状態になることも考えられます。
「疲れているけれど、まだ頑張れる」と無理を重ねると、気がついたときには深刻な健康問題になってしまうこともあります。疲労はただの「だるさ」ではなく、体が発している重要なサインです。日々の生活の中で、自分の疲労と向き合い、適切に休養をとることが、健康を維持するためには欠かせません。
参考元:東洋経済新報社「あなたを疲れから救う 休養学」






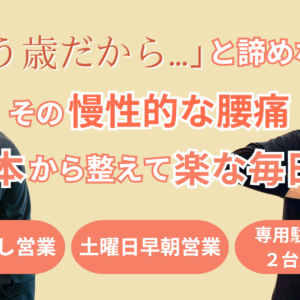
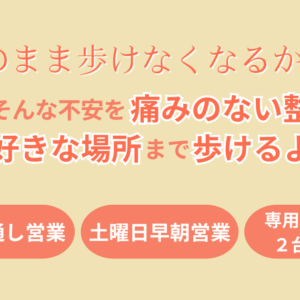
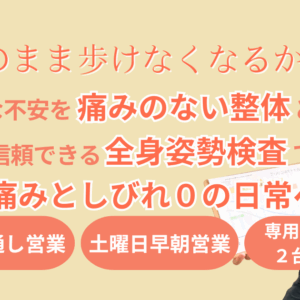





コメント