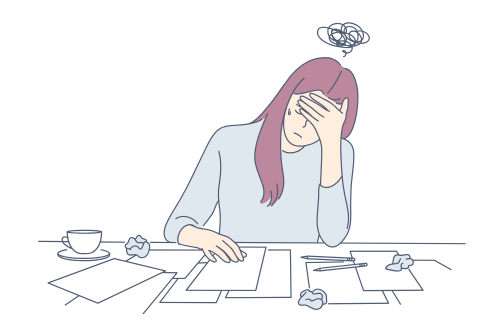
日本疲労学会の定義する「疲労」とは
そもそも「疲労」とは何でしょうか?私が所属する日本疲労学会では、疲労を次のように定義しています。
「過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う、身体の活動能力の減退した状態である。」
少々難しく聞こえますが、よく考えてみるとごく当たり前のことを言っていることが分かります。
肉体的な活動をすると、それに伴い体の活動能力は低下します。
例えば 100m走を走った直後、すぐに同じタイムで走ることはできません。 これは、走ることで身体の能力が低下した、つまり「疲労」が発生したということです。
精神的な活動でも疲労は起こります。じっとしていても頭をフル回転させると、体まで疲れることがあります。
ご予約はオンラインからでも可能です。
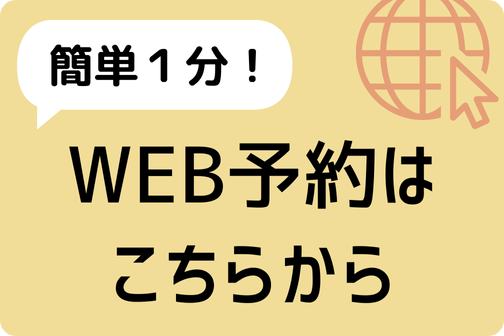
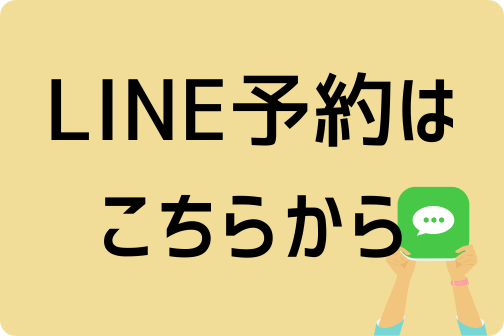
精神的な活動が肉体の疲れを生む
「精神的な疲労」が「肉体的な疲労」と密接に結びついていることは、いくつかの実験からも分かります。
例えばクレペリンテストという心理テストがあります。これは一桁の足し算を30分間ひたすら続けるという単純な作業です。
このテストは企業の採用試験や配属決定の際に使われることがありますが、心理学の実験では「精神的な負荷」をかける目的でも利用されます。鉛筆を動かすだけの軽い肉体的活動にもかかわらず、終わるころにはぐったりと疲れてしまうのです。あるいは、緊張する面接を受けたあと、「体にずっと力が入っていた」と感じたことはないでしょうか?
このように、精神的な活動は無意識のうちに肉体的な活動を引き起こし、結果として疲労につながることが分かります。
「疲労の正体」とは?
結局のところ、疲労とは「体を動かしたり、頭を使ったりすることで、本来の活動能力が下がった状態」のことです。
つまり、疲れは「体の疲れ」と「心の疲れ」がセットになっているということを理解しておくことが重要です。
参考元:東洋経済新報社「あなたを疲れから救う 休養学」






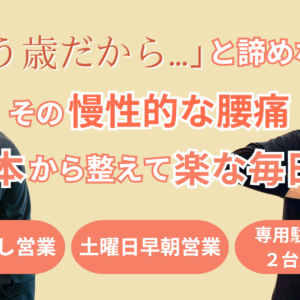
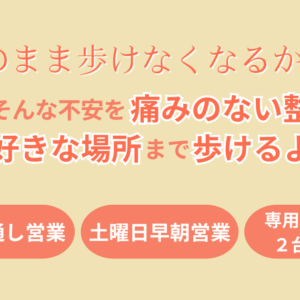
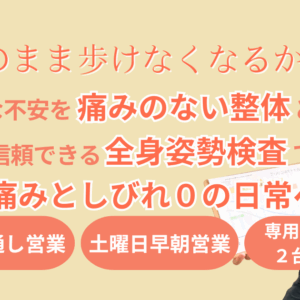






コメント